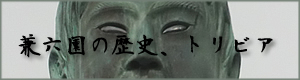瓢池(ひさごいけ)
ひさご池(瓢池)は兼六園で2番目に大きい池です。
2500平方メートル(760坪)の池に小島が1つ、滝が2つ、橋が2つあります。
ひさご池周辺は兼六園が作られる前には「蓮池(れんち)」と呼ばれ、ハスが生い茂る沼地でした。
蓮池にあった沼を利用して作られたのかひさご池で、ひさご池周辺の庭は兼六園と呼ばれるまでは蓮池庭(れんちてい)と呼ばれ、作庭されていました。
兼六園の始まりの場所であり、園内でもっとも古く作られた場所なのです。
ひさご池の名前の由来
ひさご(瓢)とは、ひょうたん(瓢箪)のことです。ひょうたんは夕顔の実です。

池の真ん中がくびれてひょうたんの形をしているので瓢池(ひさごいけ)・・。
と言われていますが、実は、ひさご池はひょうたんの形をしていません。
池の真ん中あたりにある、といわれる「くびれ」、がそもそも無いのです。
今と昔では違っていたひさご池の姿
ひさご池には現在、池の真ん中に松の木が生える小島が一つだけあります。
池の中に松の木が植えられた小島は『岩島』と呼ばれる島で、当時と同じ場所にあります。


瓢池がは、作られた当初は池に3つの小島が並ぶ形だったのです。
夕顔亭の建っている場所、海石塔のある場所、岩島(松の木の生えた島)は、かつてはそれぞれ池の中にある小島として作られていました。

「三島一連の庭」と呼ばれる作りで、
3つの島を、不老長寿の神仙島の三島(蓬莱:ほうらい、万丈:ばんじょう、瀛州:えいしゅう)になぞらえて、子孫繁栄、延命長寿、立身出世を願って作られたものでした。
3つの島のうち、夕顔亭のある小島と海石塔のある小島は、砂州でうっすら繋がっていました。
砂州がくびれとなって2つの小島が繋がっている様子がひょうたん型だったのです。

現在は、夕顔亭のある小島は完全に陸続きになり、海石塔のあった小島は日暮らしの橋で繋がることで池に突き出た半島みたいになっています。
ひさご池を当初の3島の姿に復元すればいい、という話もありますが、寿命のあるものは枯れて無くなり、石は風雪で削れ苔生し、流れは変わるもの・・。
見ている側の人もまた、年を重ねます。
同じ物、変わらない場所も、年を経て見るとまた違う面が見えたりします。
経る年月を見る、というのも日本庭園の楽しみの一つなのです。