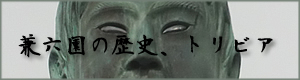おばけ灯篭(寄せ石灯籠)
花見橋から、鶺鴒島→ひねくれの松と見て、さらに進むと、平べったい傘の、崩れかけた灯篭があります。
おばけ灯篭です。

おばけ灯篭と呼ばれていますが、本当の名前は、寄せ石灯籠(よせいしどうろう)。
傘は六角形、火袋は八角形で穴は3つ(長方形が一つと丸形2つ)、火袋の台は坪野石と呼ばれる激レア石で、八角形です。
おばけ灯篭にかぎらず、兼六園の灯籠は、凍結で割れるのを防ぐために、冬場になると菰(こも:ワラで編んだゴザのようなもの)でぐるぐる巻きにされます。
菰に巻かれた、おばけ灯篭。

こんな姿だと、オバケに見えるよね。
おばけ灯篭の由来
地元の人に聞くと、おばけ灯篭の周辺に幽霊が出たので、おばけ灯篭と呼んでいる、とのこと。

しかし、昭和初期の本によると、
このあたりにはススキが一面に生えていて、灯籠に火を灯すとススキがおばけのように見えたことからおばけ灯篭と呼んだ、とあります。

サンシュユ
おばけ灯篭のそばにある木はサンシュユという木です。
早春に黄色い花が咲きます。

秋には、赤くてツヤツヤしてとってもおいしそうな実をたくさんつけます。
実に毒はありませんが、鳥も食べないほど渋くてマズいので、いつまでも赤い実を鑑賞できます。
スイリュウ
おばけ灯篭の後ろにある、とっても立派で大きな杉の木は、スイリュウ。

スイリュウの枝は、枝がしなって下向きに流れるように垂れています。大きな滝のようにも見えますし、柳の木のようにも見えます。
もしかしたら、おばけ灯篭というのは、スイリュウを柳に見立てて、柳の木の下の幽霊を表現した、演出?。