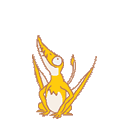ウタツサウルスは、前期三畳紀の日本の海にすんでいた魚竜類です。
魚竜類としては生きていた時代が古く、原始的な特徴を残している珍しい魚竜類です。

ウタツサウルス
学名:Utatsusaurus hataii(ウタツサウルス・ハタイイ)
分類:爬虫綱 双弓亜綱 広弓下網 魚竜上目 ウタツサウルス科
時代:中生代 前期三畳紀
体長:約3m
発掘地:日本 宮城県歌津町(現在の宮城県南三陸町) 大沢層
学名の意味:歌津のトカゲ
原始的な魚竜類
ウタツサウルスは、中生代 前期三畳紀(オレネキアン:約2億5000万年前から2億4500万年前)の海にすんでいた爬虫類「魚竜類(ぎょりゅうるい)」です。
1970年に発見され、1978年に「ウタツサウルス・ハタイイ(Utatsusaurus hataii)」の学名が付けられました。
属名は、発見地の歌津町から、種小名は、東北大学の畑井教授にちなんでつけられています。
日本の海のほか、同じウタツサウルス属と思われる仲間がカナダやアメリカでも見つかっています。

ウタツサウルスは、現在見つかっている魚竜類ではかなり原始的で、他の魚竜類では退化して無くなっている骨盤がまだ残っていて、脊椎と骨盤が関節していました。
尾ビレのヒレはあまり大きくなかったようで、尾を振って、ではなく、体をくねらせて泳いでいた、と考えられています。
状態の良い化石から、背ビレは持っていなかったことが分かっています。
本物の化石
福井県立恐竜博物館に展示されていたウタツサウルスの化石。
レプリカじゃなくて本物の化石。

左が完模式標本(亜成体の頭と胴体)、右側が副模式標本(成体の尻尾)。
別個体の組み合わせですが二つでワンセットだそう。
完模式標本。頭骨の下アゴ側。尖った三角形の頭と、小骨の多い肋骨たくさん見えます。

ウタツサウルスの左前肢(前ヒレ)。頭骨のわりに小さめ。

ウタツサウルスでは、前肢より後肢のほうが大きかったとされていますが、この化石からでは不明。

陸生生物の名残りが残る魚竜類
ウタツサウルスは前肢後肢がヒレになり、完全に水中生活に適応した体になっていますが、脊椎と骨盤が関節するなど、陸生生物の名残りが残っています。
魚竜類の祖先は陸上で生活していた爬虫類であった、ということになりますが、魚竜類の祖先と思われる陸生の爬虫類はまだ見つかっていません。

時代的にみると、爬虫類が両生類から枝分かれし、陸生動物として適応してから間もなく、なぜかまた水中(海)へ戻ったことになります。
魚竜類がなぜ海に戻ったのかはわかっていません。
古生代ペルム紀(中生代三畳紀の一つ前の時代)には水陸両生の爬虫類(メソサウルスなど)が現れていましたが、ペルム紀末の大量絶滅で多くの生物がいなくなったため、海洋生物としてのニッチが空いていたのかもしれません。